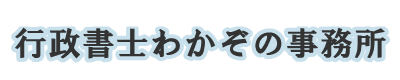建設業許可

一定規模の建設工事を請け負って建設業を営むためには、知事、または大臣の許可を受ける必要があります。忙しい建設業者の皆さまに代わり、確実な許可申請をお手伝いいたします!
建設業を事業として営むには、一定の条件に該当する場合には「許可」を取得する必要があります。
建設工事、建築物自体の安全性に加え、取引の安全を確保することで、国民の身体の安全や発注者の利益が侵害されることを防止する目的です。
弊事務所では、日々忙しく建設業を営む地域の事業者様に代わり、建設業の許可申請、変更の届出、年次決算変更届など、必要なお手続きを承ります。
申請に必要な書類は多く、揃えるだけでも大変な労力を要することです。
許可申請を専門とする行政書士にお任せいただくことで、本来の業務に専念していただくことができます。
許可取得後の各種届出に関しても、もれなく行えるように引き続きサポートすることができます。
(変更届出を行っていないと、次の許可申請が受理されなくなる場合があります!)
外国人の雇用に関しても、行政書士は在留資格の申請取次を専門としておりますので、お任せください。
建設業許可の必要な建設工事
以下の工事のみを請け負う場合は、許可の取得は必ずしも必要ありません。
【軽微な建設工事】
⑴1件の請負代金が税込・材料費込500万円未満の工事
⑵建築工事一式(総合的な企画、指導、調整の下に建築物を建設する工事)で、1件の請負代金が税込・材料費込1,500万円未満の工事、または木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事
【それ以外の建設工事】
個人、法人問わず、建設業許可を取得する必要があります。
建設業許可の区分~建設工事の金額~
【特定建設業許可】
元請として発注者から直接請け負う1件の建設工事につき、その工事の代金の全部または一部を、下請代金の額(※1)が税込5,000万円以上(※2)となる下請け契約を締結して施工しようとする場合。
※1→下請契約が2つ以上ある時はその下請代金の総額
※2→建築一式工事の場合は税込8,000万円以上
【一般建設業許可】
特定建設業以外。
元請として下請けに出す金額が上記の金額に該当しない(税込5,000万円未満/建築一式工事は税込8,000万円未満)場合。
またはすべて自社で施工する場合。
建設業許可の区分~知事と国土交通大臣~
【都道府県知事許可】
1つの都道府県のみに営業所を設けて営業しようとする場合。
【国土交通大臣許可】
2つ以上の都道府県に営業所を設けて営業しようとする場合。
「営業所」とは
「本店」又は「支店」若しくは「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」を言います。
建設業に全く無関係な支店、単なる登記上の本店、工事事務所や作業所、資材置き場など常時契約を締結する場所ではないものは、営業所には該当しません。
建設業許可の要件
【人的要件】
①常勤役員等(旧:経営業務管理責任者、経管)
建設業にかかる経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものであること
→一定の経営管理能力の有無と、適正な社会保険加入の義務の履行
②営業所技術者等(旧:専任技術者、専技)
許可を受けようとする建設業に関する一定の資格又は経験を有する技術者がいること
→建設業を営む営業所ごとに、専任で配置する必要
③誠実性
請負契約に関して「不正」又は「不誠実」な行為をするおそれが明らかな者でないこと
→法人、その役員および政令使用人、個人、その政令使用人をすべて含む
【財産的要件】
④財産的基礎等
建設業の請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
<一般建設業>次のいずれかに該当すること
ア.直前の決算において自己資本の額が500万円以上であること
イ.500万円以上の資金調達能力があること
ウ.許可申請直前の5年間に許可を受けて継続して営業した実績を有すること
<特定建設業>以下のすべてに該当すること
ア.欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
イ.流動比率が75%以上であること
ウ.資本金が2,000万円以上でありかつ自己資本の額が4,000万円以上であること
【欠格要件】
申請者、役員等、支配人又は営業所長のうち、以下のいずれかに該当する者がいる場合は、許可を受けることができません。
・破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
・不正の手段により許可を受けたこと、又は営業停止処分に違反したこと等によりその許可を取り消されてから5年を経過しない者
・許可の取り消し処分を免れるために廃業の届出を行い、その届出の日から5年を経過しない者
・許可の取り消し処分を免れるために廃業の届出を行った事業者について、許可の取消処分に係る聴聞の通知の前60日以内に当該法人の役員等若しくは政令で定める使用人であった者又は個人の使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者
・営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
・営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
・拘禁以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
・建設業法、又は一定の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
・心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定める者
・営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法人である場合においては、その役員等)が上記のいずれかに該当する者
・暴力団員等がその事業活動を支配する者
建設業許可の有効期間
許可の有効期間は5年です。
許可日から5年目を経過する日の前日をもって満了します。
引き続き建設業を営もうとする場合は、有効期間満了日の30日前までに更新の許可申請書を提出しなければなりません。
ご依頼の流れ
お客様の現状を詳しくお伺いします。
許可要件に照らし合わせながら、許可取得の可能性を検討します。
許可申請を行うことが決まったら、申請にかかる費用のお見積りをいたします。
ご検討いただき、ご依頼いただく場合は、正式にご契約となります。
許可申請に必要な書類、お客様ご自身でご準備いただく書類についてご案内申し上げます。
弊事務所で担当する書類の収集、必要に応じ行政庁担当窓口との折衝を行います。
申請書一式を作成します。
弊事務所が代理で申請手続きを行います。
申請が受理されてからの審査に係る標準処理期間は、国土交通大臣許可で約90日、都道府県知事許可で千葉県の場合約45日となっています。
通知書が「主たる営業所」に「転送不要」の条件で郵送されます。(営業所の所在確認をするため。)
許可取得後もお任せください!
許可を受けた後にも、営業所や役員などについて変更があった場合は、変更後30日以内、もしくは2週間以内に届出を行う必要があります。
申請時に届け出た事項に何らかの変更があった場合は、まず弊事務所にご連絡ください。
必要に応じ、速やかに手続きを行います。
弊事務所は、許可を受けて建設業を営む事業者の皆さま、またこれから新たに建設業許可を取得しようと考えていらっしゃる事業者の皆さまが、心置きなく本業に専念できる環境を整えるお手伝いをいたします。
いつでもお声かけ、ご相談ください。
まずはお気軽に、メールかLINEでお問い合わせください!