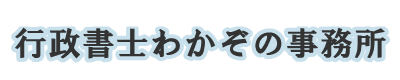宅地建物取引業免許

住宅は、人々の暮らしに欠かせない生活基盤のひとつです。
しかし衣・食とは違い、その取引には大きな金額が動くにも関わらず、一般市民には知識も経験も大いに不足している実情から、思いもよらぬトラブルに巻き込まれるケースもあるのです。
専門的な知識がなくとも、一般消費者が安全に住宅その他土地建物に関する取引が出来るようにするにはどうしたら良いか?ということで定められたのが宅建業法です。
宅地建物取引業を営むには、都道府県知事、もしくは国土交通大臣から免許を受けなければならず、またその免許は5年ごとに更新されなくてはなりません。
無免許で営業した場合には、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはその併科、という罰則があります。
免許権者は以下の区分の通りです。
<都道府県知事> 1つの都道府県内に事務所を設置する場合
<国土交通大臣> 2つ以上の都道府県の区域内に事務所を設置する場合
まずは申請者、使用人、法人の役員等に欠格事由に該当する人がいないかどうか確認します。もしひとつでも該当する場合は免許は下りません。
<欠格事由>
①破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
②宅地建物取引業免許の取消を受けて5年経過しない者
③免許取消処分にかかる聴聞手続中に免許を返納し、5年経過しない者
④禁固以上の刑に処せられ5年経過しない者
⑤禁固以上の刑の執行猶予を受け、期間が満了してから5年経過しない者
⑥特定の罪(傷害、暴行等)で罰金刑に処せられ、または猶予期間が満了してから5年経過しない者
⑦暴力団関係者
⑧申請以前5年の間に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をした者
⑨宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者
⑩成年被後見人、被保佐人
⑪未成年であって法定代理人が上記各号に該当する者
⑫役員または政令使用人のうちに①~⑩に該当する者があるもの
⑬定められた専任の宅地建物取引士を置くことができない者
宅建業を営むには必ず事務所を設ける必要があります。
自宅の一角、マンションの一室、戸建て住宅内の一室…という条件でも、事務所として認められるケースが絶対ないとは言えません。しかし原則としては独立性、社会通念上事務所とみなせるだけの外観を備えていること、また宅建業事務所として使用する権限があることが厳密に問われます。
そして各事務所には専任の宅地建物取引士を決まった割合の人数で配置しなくてはなりません。
かつては名義貸し、なども行われていたようですが、もちろん違法です。専任の宅地建物取引士とは、その事務所における専従性と常勤性を満たすものでなくてはなりません。
また取引の安全を保障するという意味で、財産的基礎も要件のひとつです。
具体的には営業保証金の供託、もしくは保証協会へ入会して弁済業務保証金分担金を支払う、このどちらかを選択することになります。
免許申請の流れ
①免許を受けるための要件を確認します。
申請者、役員、専任の取引士のうちに欠格事由に該当する人がいないか。
独立性の保てる事務所、保証金または分担金を拠出するための資金、専任の宅地建物取引士の手配…これらの要件が整ったことを確認して、申請手続きの準備に入ります。
②申請書類の作成
申請書一式に法人、事務所、代表、役員等に関連する情報を、確認しながら記入していきます。
市町村が発行する身分証明書、登記されていないことの証明書、法人の登記事項証明書、決算書類等の添付書類を収集します。
事務所に関しては詳しい地図、見取図、間取図、外観内観の写真が必要です。
③免許申請
特別な事情がある場合は、事前に担当官によく確認しておくと良いでしょう。
申請書類が揃った時点でオンライン、郵送、窓口のいずれかの方法で申請を行います。
(現在eMLIT(イーエムリット)という国土交通省の申請システムを利用することができます。)
④免許の通知
宅建業の免許申請にかかる標準処理期間は50日~60日となっています。(大臣免許は100日)
無事に審査が終了し免許が下りることになると、申請者の事務所宛てに通知のはがきが届きます。それを受けて保証協会加入手続きを行い、分担金を支払います。(もしくは保証金を供託します。)
その納付書と通知はがきを担当窓口に持参して、免許証の交付を受けます。
弊事務所の宅建業免許申請サポート
開業のご準備、もしくは通常の業務でお忙しい皆さまに代わり、宅地建物取引業の免許申請及び更新申請の手続きを行います。
要件の確認から不備の洗い出し、補正、書類の収集作成から申請代行、許可証の受け取りまで、一貫してお任せいただけます。
弊事務所へ依頼するメリット
♦各種オンライン申請に対応しております!
♦地域密着型事務所ゆえのレスポンスの速さ!
♦案件を確実にこなす誠実性!
まずは「お問い合わせフォーム」でご相談内容をお知らせください。
手続き・書類・手順・金額などのご案内、その他疑問点の解消など、無料相談にてお受けいたします。
その後、面談へと進む場合、基本的にこちらから伺いますので、弊事務所までわざわざお越しいただく必要はございません。Zoomを利用したオンライン面談も可能です。
ご依頼の内容に応じ、お見積りをご提示させていただきます。
ご納得されましたら正式にご契約となります。
ご契約書にサインを頂き、委任状、必要書類などをお預かりさせていただきます。
お見積りにて提示させていただいた報酬額の半額を着手金としてお支払いいただきます。
ご入金が確認できましたら、すみやかに業務に取りかかります。
なお、報酬の残額、窓口での申請手数料等は、申請準備が整った時点でご請求申し上げます。
業務開始後は必要に応じ、お客様に進捗状況をご報告いたします。
お客様のお時間を余計に消費しないために、おもにLINEかメールを利用したやり取りになると思います。もちろん必要であればいつでもお電話で対応いたしますのでご安心ください。
申請書類一式が整い、申請の準備ができたタイミングで、報酬残額及び申請手数料、実費等のご請求書をお送りいたします。期日までにご入金いただき、その後、申請を行います。
処理期間は50~60日(大臣免許は100日)ほどかかりますのでお待ちください。
免許が下りることになると、お客様の事務所に通知はがきが届きます。
弊事務所でそのはがきをお預かりし、保証協会への加入手続きを行います。この時、分担金のお支払いをお願いします。
そして納付書と通知はがきを窓口へ持参し、宅地建物取引業の免許証の交付を受けます。
免許証とお預かりしていた書類等をすべてお引渡しして、業務完了となります。
5年ごとの免許更新を待たずとも、その間に発生する各種変更手続きもお任せください。内容によっては事前申請が必要な事項もございます。ご自分で把握されることももちろん大事ですが、何か変更が生じた際、ご一報いただければすぐに対応いたします。
官公署への申請手続きは弊事務所にお任せ!
免許申請に限らず、行政への手続きとは、なかなかの労力と時間を取られるものです。
そこを弊事務所に依頼(丸投げ)することで、ストレスなく本業に邁進していただくのが最も効率的だと考えます。
ご相談、お問い合わせはお気軽にどうぞ。お待ちしております♪
🍀ご依頼者様に寄り添い、その方の立場で考える
🍀素早いレスポンスで出来る限りのご安心をご提供する
🍀選んで良かったと思っていただける渾身のサポート