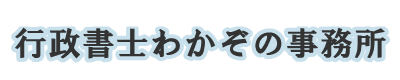遺言書作成

ご自分とご家族の安心を形に~遺言書を書いてみませんか~
遺言書を書くということ
「自分が亡くなった後、自分の築いた財産は誰の手に渡るのだろう?」
「後に残していく家族の行く末が心配だ」
「家族仲が良いから財産の取り合いなんてことにはならないと思うけど…」
資産家や、経営者でなければ遺言書なんて必要ない、そう思っていませんか?
確かに元気なうちは、自分がいなくなった後のことなんて、まだまだ先のことと考えてしまいがちです。
ですが、実際の相続の場面では、遺言書がないがために残された家族が大変な思いをするケースが多いのも事実です。
また気にかかりながらもそのままにしてしまった負の財産がある場合や、どうしても財産を渡したくない相手がいるといった場合も、遺言書を残しておけば家族を助け、自分の希望を叶えることができるかもしれないのです。
そしてもうひとつ、大事なことは、「遺言書は元気な時にしか作れない」ことです。
認知機能が衰えてから、もしくは自分の意思をはっきり表すことができなくなってから遺言書を書いたとしても、法的に有効と認められない可能性があるのです。
ですから遺言書の作成はぜひ元気なうちに取り掛かることをおすすめいたします。
状況が変わって書き直すことになったとしても、構いません。一度書いても何度だって書き直せるのです。ぜひ、ご自分の希望を遺言書に盛り込んで、安心を手に入れたうえで人生を歩んでいかれませんか?
こんな時は弊事務所がお手伝いできます!
・遺言書を書きたいけれど…
・具体的にどこから手を付けて良いか分からない。
・何をどう書いていいか分からない。
・公証役場とのやり取りが負担になってしまう。
ご相談内容がはっきりしていなくても大丈夫です。一緒に考えていきましょう。
遺言書の作成が、ご家族へ贈る最高のプレゼントとなりますように。そしてその後のご依頼者様の人生が、不安なく大いに安らいだ前向きなものとなりますように。
お問い合わせはどうぞお気軽に♬
「遺言・相続」がテーマのお役立ちブログはこちら
遺言書作成サポート
遺言書を書くには、財産の内容を把握したり、相続人の確定をしたりといった準備が必要になります。
弊事務所では、そういった遺言書作成の準備段階から遺言書の完成まで、フルサポートを行っています。
(一部の業務のみのご依頼も承ります。)
まずは遺言書に書きたい内容をうかがいます。
この財産の洗い出しにおいて、誰にどのように何の財産を残すかが見えてくると思います。
そして法定相続人の調査を行って相続関係説明図を作成します。
残される家族に特に配慮が必要な人がいる場合、法定相続人の遺留分が気になる場合なども、細かにヒアリングを重ねて遺言書の内容を詰めていきます。
自筆証書遺言は「すべて自筆」が原則となっています。原案をもとに自筆で書いていただき、完成です。
財産目録についてはパソコン等で作成したものも認められるようになっていますので、今後社会の要請に応じて、すべてパソコン等で作成した文書でも可、となる日が来るかも知れません。
☆「デジタル遺言書」について!
「保管証書遺言」という新しい方式を設けて、パソコン等で作成した遺言書を法務局で保管できる制度が検討されています。(2026年1月現在)
遺言を公正証書とする場合は、原案作成中から公証役場へ事前相談を行います。
作成日時の予約、証人の手配など、公証役場とのやり取りは全て弊事務所で完結するようにします。
無事に遺言公正証書の正本と謄本をお渡しして完了です。
「遺言書の書き方が分からない」
「まず何からやれば良いか分からない」
そんな時は…
お気軽にお問い合わせください♬
代表的な遺言書
| 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
|---|---|---|
| 作成方法 |
遺言者が全文を自筆で書く。 |
公証役場にて、証人立会いのもと、遺言者が遺言の内容を口述し、公証人が確認のうえ、公証を行う。 |
| 効力 | 形式上の不備があると無効となるおそれがある。正確な日付、署名、押印が必要。 | 形式、内容ともに公証人が確認を行うため、無効になることがない。 |
| 保管 | 原則自宅などで保管。あるいは法務局の保管制度を利用する。法務局に保管した遺言書は写しの再発行が可能。 | 原本は公証役場で保管。正本、謄本を自宅などで保管する。写しの再発行が可能。 |
| 検認 | 自宅などで保管した場合は、開封前に家庭裁判所での検認の手続きが必要になる。 | 検認の必要なし。 |
| 費用 | 法務局での保管は3,900円/通 | 所定の手数料がかかる。 |
⑴作成のポイント
全文を自筆で書く必要があります。
正確な日付(○○年〇〇月〇〇日)と、遺言者の署名・押印(できれば実印)のどれかが欠けると無効となります。
財産は特定できるよう、(不動産なら登記簿どおりの記載で)ひとつずつ細かく記します。
財産目録のみ、パソコン等で作成したものも認められますが、全てのページに署名・押印は必要です。
⑵自筆証書遺言の保管と活用
自宅で遺言者の手元に保管するか、遺言執行者を指定したのであれば、その人に預けるという選択肢もあります。
自宅での保管には、紛失や改ざんのおそれがあります。またせっかく書き残しても、保管場所によっては発見されない、ということも。
ですので、あらかじめ近しいまわりの誰かに遺言書があることを伝えておきましょう。
相続開始後に遺言書を開封する際には、その前に家庭裁判所で検認の手続きを行う必要があります。検認をせずに開封すると、過料が科される場合があります。
⑶法務局の自筆証書遺言書保管制度について
遺言者の本籍、住所地、所有する不動産の所在地いずれかを管轄する法務局内の遺言書保管所で、自筆証書遺言書を保管してくれる制度です。
利用申請には遺言者が自ら窓口に出向く必要がありますが、形式的なチェックを行ってくれるので、無効になることはほとんどなく、紛失した際も写しの再発行が可能です。ただし、遺言の内容に関しての確認は行いません。
遺言者が死亡した事実を遺言書保管官が把握した時点で、あらかじめ指定した通知者に遺言書が保管されている通知が届くので、万が一誰にも伝えずに遺言者が亡くなった場合も、遺言書が発見されないということはありません。
法務局で保管した場合、相続開始後の遺言書の検認手続きは不要となります。
手数料は1通ごとに3,900円がかかります。
法務局HP「自筆証書遺言書保管制度について」
⑴公正証書遺言の作成の流れ
①遺言の原案作成
ご自分で、または専門家に相談しながら遺言書の原案を作成します。もしくは直接、財産の内容や相続人の情報となる資料を公証役場に持参して、公証人と相談しながら作成することもできます。
この事前相談において、形式、内容ともに公証人が確認をしてくれるので、無効とされるおそれがありません。
②公正証書遺言を作成する日時を予約する
遺言書の原案が完成したところで、公正証書遺言を作成する日時を予約し、証人2名の手配をします。作成は公証役場に出向いて行いますが、遺言者の状態により、自宅や病院などへ公証人に出張してもらい、そこで作成することも可能です。(出張費は別にかかります。)
③当日の手続き
遺言者本人が、証人2名の立会いのもと、公証人に対し、遺言の内容を口述します。
公証人はあらかじめ決めておいた遺言書の原案を、証人2名にも読み聞かせ、又は閲覧させ、遺言の内容と相違ないことを確認させます。
その後、遺言者および証人2名が遺言公正証書の原本に署名・押印します。
そして公証人も署名し、職印を押捺することによって、遺言公正証書が完成します。
⑵公正証書遺言の保管
遺言書の原本は公証役場に保管され、遺言者の手元には正本と謄本が渡されます。
自宅で保管するか、遺言執行者を指定したのであれば、その方に正本を預け、相続開始後は確実に遺言執行者に連絡がいくようにしておくと良いでしょう。
万が一紛失した場合は、再発行を請求できます。ただし、遺言者本人の存命中は、本人以外に再発行の申請はできません。
相続開始後は、相続人など利害関係者が遺言書の有無を問い合わせることや、謄本の請求を行うことができます。
⑶利用にかかる費用
公証役場の手数料は、目的とする財産の価額により変わってきます。
そして相続人の人数、作成する遺言公正証書の枚数などによっても違うので、事前に公証役場のWEBサイトか直接確認してみると良いでしょう。
また、公証役場以外の場所に、公証人が出張して作成する場合、交通費と日当が加算されます。
お問い合わせはどうぞお気軽に♬
「遺言・相続」がテーマのお役立ちブログはこちら
🍀ご依頼者様に寄り添い、その方の立場で考える
🍀素早いレスポンスで出来る限りのご安心をご提供する
🍀選んで良かったと思っていただける渾身のサポート